データ
1936.2.15
額面 6pf
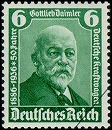
Gottlieb Daimler
1834-1900
機械技術者
1936.2.15
額面 12pf

Karl Benz
1844-1929
機械技術者
1936.5.4
額面 6pf
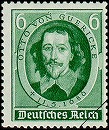
Otto v Guericke
1602-1686
物理学者
政治家
1940.11.26
額面
6+4pf

Emil Behring
1854-1917
医学者
1944.1.25
額面
12+38pf
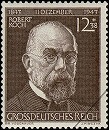
1843-1910
細菌学者
| 切手 データ |
切手画像 | 名前 | 略歴 |
| 発行 1936.2.15 額面 6pf |
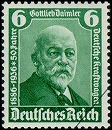 |
G・ダイムラー Gottlieb Daimler 1834-1900 機械技術者 |
彼は大形で、騒音の大きいオットーのエンジンに代わる小型で、軽量で、高速度回転によって出力を増大する高速ガソリンエンジンをつくろうとした。開発の過程で回転むらの欠点を解消するために4行程のエンジンをつくった(1885年特許取得)。1885年にこのエンジンを2輪車に取り付けてみた。これはモーターサイクルの原型となった。トロッコ、船などに続き、1886年に4輪馬車の馬の代わりにエンジンを載せた。それからは自動車に興味を持ち、1890年にダイムラー自動車会社を設立した。 |
| 発行 1936.2.15 額面 12pf |
 |
K・ベンツ Karl Benz 1844-1929 機械技術者 |
1871年にマンハイムに工作機械工場をつくり、内燃機関の研究を始めた。自転車に搭載できるようなエンジンを目指した。この当時石炭ガスエンジンがあることを知ったが、それは熱効率が悪く、馬力も弱かった。ベンツはまずこの開発研究を始めた。1878年石炭ガスエンジンを開発。さらに3輪車、4輪車とそれに搭載できる小型エンジンの開発を始めた。その過程で小型化にはガソリンエンジンが適していると考えた。圧縮してガソリンの濃度を上げ、小型で強力なガソリンエンジンの開発に成功した。 1885年3輪自動車を完成した。1886年には彼の自動車特許が発効。1883年自動車商会を設立した。 |
| 発行 1936.5.4 額面 6pf |
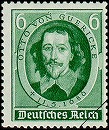 |
O・ゲーリケ Otto v Guericke 1602-1686 物理学者 政治家 |
若くしてマグデブルク市会議員に選出され,30年戦争の戦渦からの復興に努力した結果、1646年から30年間同市長を務めた。その余暇を科学の実験にあて、外交活動などの際にも科学実験を発表した。真空が存在するのか確かめるために自ら真空ポンプを発明(1640頃)し、銅球を使った実験を重ね、1654年レーゲンスブルクの国民議会の際に有名なマクデブルクの半球の実験を行った。半径400mmの2つの銅製半球を合わせ、排気すると、16頭の馬に引かせても離れなかった。その後、真空中ではローソクの火が消えること、動物が生きられないこと、ブドウが半年間も新鮮なまま保たれること、音が伝わらないことなどを実証した。また球の中の空気の有無、圧力、温度により、球の重量が変わることも発見した。これは後のボイルの法則につながる実験である。R.ボイルはこれらの結果を知って気体の研究を始めたとも言われている。 |
| 発行 1940.11.26 額面 6+4pf |
 |
E・ベーリンク Emil Behring 1854-1917 医学者 |
生家が大変貧しかったため学費の要らない陸軍医科専門学校に進学し、軍医として陸軍医務局所属。創傷に対し有効な殺菌薬はないか検討の上実地で試し、ヨードホルムの殺菌性を発見。その後、軍を辞め、ベルリン衛生試験所に移り、R. コッホの助手として衛生学を学ぶ。当時、F. レフレル (1852-1915) が純粋培養(1884)に成功したジフテリア菌を使い、血清療法に成功。その後破傷風についても同療法が有効であること実証した。 1890年12月ドイツ医学週報第49号に「動物におけるジフテリア免疫と破傷風免疫の成立について」を北里柴三郎との共著で発表。 第50号では自身の名前のみでジフテリアについてデータを発表。 1901年 「ジフテリアに対する血清療法の研究」で第1回ノーベル生理学・医学賞を受賞。 受賞に際し、自分だけの功績ではなく、北里あっての結果であることを述べたとされる。 |
| 発行 1944.1.25 額面 12+38pf |
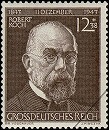 |
R・コッホ Robert Koch 1843-1910 細菌学者 |
28歳の誕生日に妻から顕微鏡を贈られたのをきっかけに細菌の研究にかかった。そして5年後炭疽菌を発見(1876)。ここでは炭疽病の病原菌の増殖、感染・発病の条件・伝播経路を見出し、特定の微生物が特定の病気をひきおこすことを初めて証明するものとして世界を驚かせた。やがてベルリンに職を得て、研究のための設備、費用が整うと彼を慕う若い研究者が世界中から集まるようになった。その代表がガフキー、レフラー、ベーリンク、エールリッヒ、北里柴三郎などである。「一つの病原菌が一つの伝染病をひきおこす」と考えたコッホは1種類の細菌の純粋培養法を研究し、肉汁と寒天による方法を見つけ、結核菌(1882)、コレラ菌(1883)などを発見した。この功績により1905年にノーベル生理学・医学賞を受賞。その他の業績として破傷風菌の発見(1878)、連鎖状球菌の発見(1881)、結核診断のためのツベルクリンの創製(1890)、ペスト菌や睡眠病菌の伝播経路解明などがある。
|
| 切手 データ |
切手画像 | 名前 | 略歴 |
| 発行 1949.12.14 額面 10+5pf |
 |
パラケルスス P.A.T.von Hohenheim 1494?-1541 医者 錬金術師 |
ドイツ系スイス人。それまでの古い医学の伝統的理論、実践的方法の欠点を認め、新しい錬金術(化学)を創始した。錬金術の目的は病気を癒す薬の創成であると考え、さらに治療に化学薬品を用いる医化学への道を拓いた。彼のつくった医薬品には毒性のあるものもあったが、今までに無い治療効果を示すものもあった。やがて時代は本格的な化学治療へと移っていった。彼は古典的医学に対して激しい攻撃を行ったためにバーゼル大学の教授職を失うことになった。以後各地を放浪しながら著作と医療に携わった。後年彼は「パラケルスス」と自称したが、これは「古代ローマの名医ケルススを超える(凌ぐ)」という意味であるという。 |
| 発行 1951.12.10 額面 30pf |
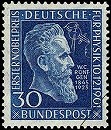 |
W・レントゲン Wilhelm Röntgen 1845-1923 物理学者 |
1895年11月8日、クルックス管を用いて陰極線の研究をしていたレントゲンは、机の上の蛍光紙の上に暗い線が表れたのに気付いた。この発光は光照射によって起こるが、クルックス管は黒いボール紙で覆われており、既知の光は遮蔽されていた。これにより、目には見えないが、光のようなものが装置からでていることを発見した。実験によって1000ページ以上の分厚い本や金属も透過するが鉛には遮蔽されることがわかった。光のようなものは電磁波であり、この電磁波は陰極線のように磁気を受けても曲がらないことからレントゲンは放射線の存在を確信し、数学の未知の数をあらわす「X」の文字を使いX線と名付けた。 |
| 発行 1952.7.25 額面 30pf |
 |
N・オットー Nikolaus Otto 1832-91 機械技術者 |
C.ホイヘンスが考案した内燃機関はE.ルノアールやA.ロシャにより、ガスと空気の混合気を使って実用化された。さらにオットーはそれらを改良して4行程の「オットーサイクル」と呼ばれるガスエンジンを開発(1864)。それは20世紀初頭までは内燃機関を代表するものであった。 |
| 発行 1952.10.25 額面 30pf |
 |
J・P・ライス Johann Philipp Reis 1834-74 物理学者 発明家 |
「光が空気中を伝わるように、人の声も遠くに伝えられるはずだ」と考えた彼は、「音」を「電気信号」に変えて伝達し、それを再び「音」に戻す装置を考えた。まずプラチナ線が付けられているブタの皮膜を張った送話器を作り、そのプラチナ線を音の電気信号を流すためのバネに接触させた。次に針を電線に巻きつけた電磁石をバイオリンにつけて受話器とした。そしてフランクフルトの物理学会で公開した(1861)。送話器の前でバイオリンを鳴らすと受話器のバイオリンが鳴った。それは音楽のような連続音を伝送することはできたが、まだ人間の生の音声の伝達には不十分で、実用には供せなかった。ライスはこの装置を"Telefon(電話)"と名づけた。ライスはG.ベルの電話の発明(1876)の報に接することなく亡くなった。 |
| 発行 1953.5.12 額面 30pf |
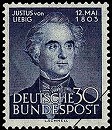 |
J・リービッヒ Jusutus Liebig 1803-73 化学者 農芸化学者 |
リービッヒは父親の影響で元々化学好きであったが、激情的な性格に加えて下宿先で爆発騒ぎを起こしたり、学生運動への参加など問題があった。パリ大学へ入学、A.v.フンボルトらの知遇でゲイ・リュサックの研究室に入り、初めて近代化学に接した。ギーセン大学に職を得た。ここで講義と学生実験を組み合わせた近代的化学の体系的教育を創始した。主な業績としては異性体を発見、有機化合物の元素分析方法大幅改良、ベンゾイル基の発見、エチル基の発見、農芸化学、生化学分野の研究、肉汁の保存食発明などがある。その他リービッヒ冷却管に名を残す。多くの学生を呼び集めたリービッヒの講義はさぞかし名調子であったに違いない。生涯無二の親友ヴェーラーは有機化学への道を指し示したが、実際にこの世界に分け入ることを可能にしたのはリービッヒであった。これこそが彼の最大の功績であったと言えるかもしれない。
|
| 発行 1953.11.2 額面 20+10pf |
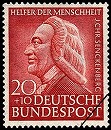 |
J・ゼンケンベルク Johann Christian Senckenberg 1707-1772 医者 |
ゲーテ「詩と真実」第1部第2章から抜粋。「ゼンケンベルク家には3人の兄弟がいて、彼らは住んでいた場所ハーゼンガッセから世間では3匹のウサギというあだ名で呼ばれていた。そのうち、次兄も医者で、極めて高潔な人物であったが、ほとんど臨床には携わらなかった。街で見かけるときは、いつ見ても瀟洒な服装をして、足早に、だが、いくぶんよろけながらジグザグな歩き方をした。このような歩き方を見た口さがない人たちは死霊を避けようとしているのだと陰口をたたいた。しかしこんな冗談やいろいろなふざけ半分の陰口も、すべて最後には彼に対する畏敬の念に変った。それは、宏壮な邸宅を、中庭や庭園の付属物をいっさい付けて、医学施設に寄付したからで、そこにはフランクフルト市民のための病院、植物園、解剖室、化学実験室、図書館などがあり、それら施設はどんな大学と比較しても恥ずかしくないくらい完備していた」 それらは3ヘクタールもの面積を擁し、当時における最大規模のもので、現在はフランクフルト大学に包含されている。 |
| 発行 1961.8.3 額面 8pf |
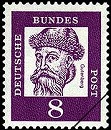 |
J・グーテンベルク Johannes Gutenberg 1400頃-68 発明家 金細工職人 |
1447年にヨーロッパにおいて総合的な活版印刷技術(具体的には活字合金製の金属活字と油性インクの使用技術)を実用化し、初めて旧約・新約聖書(ラテン語版)いわゆる『グーテンベルク聖書』を印刷(1454)したことで知られる。グーテンベルクは一般的に「活版印刷技術の発明者」と呼ばれているが、詳細に関しては議論がある。ただグーテンベルクが印刷に関するすべての技術を発明したわけではないにしろ、彼が種々の印刷技術を改良し、統合した最初の人物であることに関しては疑いがない。 グーテンベルクの偉大さは、先行する技術を統合し、活字合金の製造と活字の製作を行い、油性インクと新型の印刷機を用いることで総合的な印刷システムを完成させたことにある。 彼の開発した印刷システムは急速に普及して、大量の印刷物を生み出し、出版革命への引き金となり、ルネサンス期における情報伝播の速度を飛躍的に向上させることになる。ルターの宗教改革の成功にも大いなる貢献をしたといわれている。
|
| 発行 1955.2.23 額面 10pf |
 |
C・F・ガウス Johann Carl Friedrich Gauss 1777-1855 数学者 天文学者 物理学者 |
子供の頃から神童ぶりを発揮。小学校での1から100までの足し算の逸話は有名であるが、後年彼はこの話を好んだそうである。生涯に実に多くの仕事を行った。以下項目をあげる。素数定理成立の予想(およそ100年後に証明)/最小二乗法/正17角形の作図/代数学の基本定理/一般楕円関数/整数論/円周等分多項式/複素積分/ガウス平面(複素平面)/統計学における正規分布の法則を確立/微分幾何学の創始/ガウスの線束定理/電磁気量の単位系を確立/磁界の絶対測定法/電磁式電信機/ガウスの定理。ガウスは援助で研究生活をしていた。それを不満と思っていたわけではなく、生活にも困っていなかったが、数学そのものがそれほど世の中の役に立つとは考えていなかった。そのため、彼は天文学者になることを願うようになり、小惑星ケレスの軌道決定の功績が認められてゲッティンゲン天文台長になった。そこでも数々の発見を行っている。ガウスにとっては研究で美しい結果を得ることが最大の報酬であった。ガウスは信心深く、保守的で打ち解けない厳粛な人であった。彼は生涯2度結婚しているが、それらは決して幸福ではなかった。溺愛した先妻には先立たれ、後妻も長患いの末に亡くなった。先妻の死による精神的ショックは大きく、生涯回復することはなかったという。
|
| 発行 1957.2.22 額面 10pf |
 |
H・ヘルツ Heinrich Hertz 1857-94 物理学者 |
マックスウェルは電気と磁気の作用を統一して表す方程式を示し、電場と磁場が交互に相手を発生させながら空間を波となって伝わってゆくことを理論的に示した。これが「電磁波」である。ヘルツはこのマックスウェルが理論的に予言していた電磁波を実験によって検出した(1888)。彼は火花放電を起こして電磁波を発生させ、それが横波であることを示した。また電磁波が反射、屈折、偏りなど光と一致する性質を持つことも明らかにした。その他に光電効果の発見や力学の基礎原理研究などがある。 |
| 発行 1958.3.18 額面 10pf |
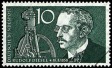 >>画像拡大 |
R・ディーゼル Rudolf Diesel 1858-1913 機械技術者 発明家 |
当時、従来のガソリンエンジンは燃焼前に空気と燃料を混合するのでノッキングを起こしやすくなり、圧縮比を大きく出来ない制限があった。この制限をなくすことが開発(特許)の鍵であった。着火に合わせて燃料を送ることにより、機械的制限がなくなった。こうして圧縮するだけで自己着火するエンジンを開発した。発明品はディーゼルエンジンと呼ばれ、大型化に適していることから、自動車、船、鉄道、油田、鉱山、工場、パイプラインなど広い分野で使われるようになった。1913年9月29日彼はイギリスでの打ち合わせのため、北海を渡るフェリーに乗ったが、まもなく行方不明になった。遺体は2週間以上たって発見された。死因は自殺説、あるいはイギリスへ技術が渡ることを恐れたドイツ官憲による暗殺説などがあるが、真相は不明である。
|
| 発行 1959.3.28 額面 10pf |
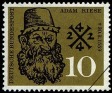 |
A・リーゼ Adam Riese 1492-1559 数学者 |
生前3冊の数学書を出版。その中には子供向けにもなるものや実業家や職人の徒弟用もあり、後者は現在まで114版も出版を重ねている。1992年になって発刊された教科書Cosは中世と近代の代数学をつなぐ内容とされている。リーゼは著書を、当時の慣習であったラテン語ではなく、ドイツ語で書いたが、これは特筆すべき事である。これにより彼は多くの読者を得たばかりでなく、M・ルター(1483-1546)と同じようにドイツ語の標準化に貢献した。
|
| 発行 1959.5.6 額面 40pf |
 |
A・Frh・v・フンボルト Alexander Freiherr von Humboldt 1769-1859 博物学者 地理学者 探検家 |
プロイセン貴族の家系。W. v.フンボルトの弟。1799年南米の探検調査に乗り出し、様々な動植物の調査を行った。これらの体験を活かし、動植物の分布と緯度や経度あるいは気候などの地理的な要因との関係を説き、近代地理学の方法論の先駆的業績とも言える「コスモス」を書いた。彼の名声はヨーロッパ中に轟き、ナポレオンに次いで有名な人物とも言われた。彼は熱帯アメリカの山地における調査によって自然地理学と地球物理学の基礎を築いた。彼の写実的記録は科学の分野に大きな功績を残した。また、ガウスとともに地磁気の研究を行い、地球の磁力の強さが極から赤道に向かって減少することを発見(1836)。C.ダーウィンはフンボルトの本を読んで感激し、ビーグル号の航海に参加したのであった。そのことだけでも、フンボルトの果たした役割は大きいと言える。 |
| 発行 1966.12.13 額面 30pf |
 |
W・v・ジーメンス Werner von Siemens 1816-92 電気技術者 実業家 物理学者 |
14人からなるジーメンス兄弟の長兄。1848年、機械工のハルスケとともに、ジーメンス・ハルスケ社を設立。1866年、それまでの永久磁石を用いた発電機から進んで、初めて電流によって界磁を励磁する方式の自励発電機を開発。自励発電機については同時期に多くの開発があり、誰が先駆者であったのか実のところ定かではない。しかし設計から開発まで一貫して多くの改良をおこない、実用的な自励発電機にまで仕上げたという点でジーメンスの評価が高い。その他電車(電気機関車)(1879)、電気製鋼法(1880)、路面電車(1881)の発明などがある。
|
| 発行 1980.5.8 額面 60pf |
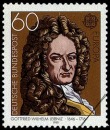 |
G・W・ライプニッツ Gottfried Wilhelm Leibniz 1646-1716 哲学者 数学者 外交官 |
彼は17世紀の様々な学問(法学、政治学、歴史学、神学、哲学、数学、経済学、自然哲学(物理学)、論理学等)を統一し、体系化しようとした。その業績は法典改革、モナド論、微積分法の発見、ベルリン科学アカデミーの創設等々、多岐にわたる。哲学の分野では 世界は無数の「真の一なるもの」つまり「モナド」によって作られていて、その頂点に神が位置するというモナド論を展開した。微積分法はI. ニュートン(発見:1669年;公表:1687年)とは独立に発見(1684-86)し、それに対する優れた記号法を与えた。現在使われている微積分の記号はd、∫ など、彼によるところが多い。その他物理学、数学上の業績がある。しかし、上記と同等か、あるいはそれ以上に重要な業績は今日の論理学における形式言語に当たるものを初めて考案したことである。 |
| 発行 1980.5.8 額面 50pf |
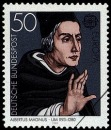 |
H・A・マグヌス Heilig Albert Magnus 1193-1280 神学者 哲学者 化学者 博物学者 医学者 |
カトリック教会の聖人(列聖は1931年)で、普遍博士と称せられる。トマス・アクィナス(1225頃−1274)の師としても有名。パリ大学やケルンのドミニコ教会の学校など各地で神学と哲学の教鞭をとった他、教会行政にも手腕を発揮した。晩年は主にケルンを中心としてドイツ各地で活動した。生活態度は真面目で質素。学問だけでなく、経営の才能もあり、財政難だった教区を立て直している。マグヌスはアリストテレス哲学を広めたが、これにより当時イスラム圏に比べて大きく遅れをとっていたヨーロッパの学問思想が大きく進展したと言われる。彼は教会の仕事に忙しく、しばしば学問的研究が中断させられたが、多くの著書を残している。化学者として1250年の著作にヒ素について言及し、その発見者とされる。彼は書斎に閉じこもるだけではなく、野外に出て観察し、実験室で研究を行う博物学者、実験科学者でもあった。 |
| 発行 1982.8.12 額面 80pf |
 |
J・フランク 1882-1964 物理学者 M・ボルン 1882-1970 物理学者 数学者 |
J・フランク James Franck
G.ヘルツ(1887-1975)と共同で電子を加速して気体原子に衝突させ、その際の電子のエネルギー損失量はちょうど原子の線スペクトルに現れる光のエネルギーに一致した(1914年)。このことからボーアの原子構造論(1913年)がやがて正しいとされるようになった。
M・ボルン Max Born ミクロの対象を記述する量子力学の基本方程式である波動方程式の解:波動関数は電子の存在確率を表すことを提唱。量子力学ではニュートン力学と異なり、電子の位置を完全には決定できず、統計的な確率としての記述にとどまると考えた。これに対してはアインシュタインからは真っ向から反対攻撃を受けた。 W.ハイゼンベルク、W.パウリ、J.L.ノイマンは門下。またイギリスの歌手オリビア・ニュートン・ジョンは孫である。 |
| 発行 1971.8.27 額面 25pf |
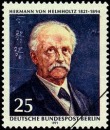 |
H・v・ヘルムホルツ Hermann von Helmholtz 1821-1894 物理学者 生理学者 数学者 哲学者 |
19世紀半ばのドイツ科学を代表する科学者。彼の研究は物理学から生理学まで多岐にわたる。物理学の分野では熱の仕事当量に関する研究から熱力学の第1法則を導き出した。1847年、この成果をベルリン物理学会にて論文「力の保存について」として発表。さらに、熱力学に関する知見を化学に応用し、エネルギー保存の法則として確立した。生理学の分野では神経興奮の伝導速度測定、検眼鏡の発明の他、生理光学、音響生理学における貢献が大きい。その他、流体力学において、渦の運動に関する数学的原理の確立、電気2重層の理論、運動ポテンシャルの研究など、実に多くの分野で重要な貢献をした。西ベルリン1971年発行。 生誕150年。 |
| 発行 1984.6.19 額面 80pf |
 |
F・W・ベッセル Friedrich Wilhelm Bessel 1784-1846 数学者 天文学者 |
ハレー彗星の軌道計算の改良や多くのの恒星データの研究が認められて、29歳でケーニヒスベルク天文台長に任命された(1813)。ここで彼は50,000個以上の恒星の位置を測定した。これらの研究で積んだ経験からさらに彼は恒星の視差を用いてその星までの距離を計算するという偉業を史上初めて成し遂げた(1838)。さらにベッセルの測定によって、恒星シリウスとプロキオンの運動にずれがあることも明らかにし、これらの恒星のずれは目に見えない伴星の重力によるものではないかと推定した。これは観測されていない伴星の存在を位置測定によって正しく指摘した最初の例であった(1841)。その他の業績としては 天王星の外側の惑星の可能性示唆(1840)や地球の正確な形状決定(1841)などが挙げられる。ベッセルは大学教育を受けなかったにも関わらず、当時の天文学界で大きな位置を占める存在となった。 |
| 発行 1988.7.14 額面 80pf |
 |
L・グメリン Leopold Gmelin 1788-1853 化学者 医学者 |
18〜19世紀、4世代に亘り、一族から何人もの化学関係の重要人物を輩出した家系の中の最高峰。 J.F.グメリン(独;化学・植物学・医学者;1748-1804)の末子。業績として最も有名なのは1817年に出版した「無機化学事典」である。ラボアジェ(仏;化学者)以降の未整理の化学知識を体系づけた功績は大きいと言われる。その他の業績としては鉱物の分析、フェリシアン化カリウムの発見(1822)のほか、1820年以降F.ティーデマン(独;生理学・解剖学者)との共同による有機化学、生化学関係の重要研究が多い。またドイツの教科書として初めて、有機化学、エステル、ケトンなどの名称を導入した。F.ヴェーラー(独;化学者)を化学の道へ進ませたのは彼である。 切手には若き日のL.グメリンの肖像と背後の書籍の背文字にI、In、Mo、Nなどの元素記号が見られる。 |
| 発行 1992.3.12 額面 100pf |
 >>画像拡大 |
A・S・マルクグラーフ Andreas Sigismund Marggraf 1709-1782 化学者 薬剤師 |
(中央の人物)インドで発見(12世紀)された亜鉛精錬技術は中国を経て、1737年にイギリスに伝わり、1743年 ヨーロッパ初の亜鉛工場が建設された。また同年スウェーデンでも亜鉛を分離することに成功。これに対して1746年マルクグラーフは他の2国とは独立して金属亜鉛を得る。 コークスと酸化亜鉛とを空気を断って加熱し、成功。この手法が金属亜鉛の大規模生産へとつながる。このため、彼こそが亜鉛の発見者だと言われることがある。その他、砂糖大根から甜菜糖を発見(1747)。カリウムとナトリウムを炎色反応の色の違いから区別(1758)。蛍石の研究(1768)。有機化学、無機化学、分析化学の分野で多くの研究がある。
|
| 発行 1992.4.9 額面 140pf |
 >>画像拡大 |
J・アダム・シャール J.A.Schall 1592-1666 天文学者 |
中国名で「湯若望」と名乗った。1622年、中国の西安に渡航し、1627年に北京に赴き、布教に従事。月蝕を予測し、見事に的中したことから名声を博し、崇禎帝に召された。徐光啓と共に西洋天文学書を翻訳し、『崇禎暦書』として宮廷に提出(1642)。その傍らで望遠鏡や大砲などを製造。1644年、清が中国を支配するようになると、西洋天文学による暦の作成を命じられ、翌年『時憲暦』を完成して献上。1646年には天文台長官に任じられた。元代を除き、中国で正式な官吏となった初の西洋人。しかし、伝統的な天文学者や元代以来のイスラム天文学者の嫉妬を買い、失脚。北京で客死。
|
| 発行 1992.6.11 額面 100pf |
 |
G・Chr・リヒテンベルク Georg Christoph Lichtenberg 1742-1799 物理学者 文筆家 |
30年にわたり、ゲッティンゲン大学の物理学教授を務めた。リヒテンベルクパターン(電場を与えた絶縁体の板の上に軽い粉を一様にまいて放電させ、粉の分布により得られる図形)発見(1777)。その他 電気の正、負の名称を導入している(1779)。生来背中が曲がっているというハンディキャップをものともせず、いつも軽快に世界を見て、文筆家としても活躍した。周りにはいつも好学の若者がいた。ゲーテから何度か親交を求められたが、ひややかにあしらった。かなりのヘソ曲がりでもあったようだ。生涯独身で通すつもりでいたが、子供がいることを心配した大学当局の一計でやむなく結婚する破目になったという逸話がある。また女性の下着の収集が趣味であったという。 |
ドイツの科学者の解説文はドイツ部会員のT・N氏の協力によります。