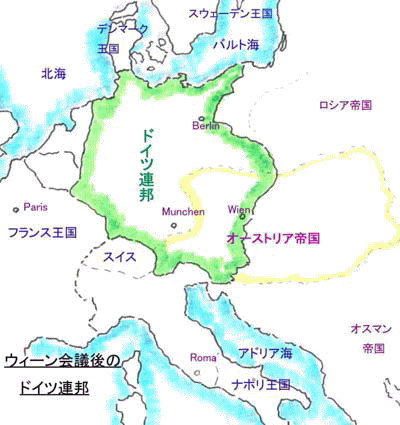
表題は初代世話人の故牧泰久氏が部会報第62号に掲載したものです。
氏の記述は平易で分り易く整理されているので、複雑な時代背景と統一への過程がよく理解されます。
この寄稿文をWEB向きに整え、背景地図、切手画像などを配置しビジュアル的に紹介します。
1815年のウィーン会議はナポレオンによって分裂させられたドイツを統一の方向へ進める…つの契機にはなった。唯この会議は統一への形成には程遠く、オーストリアとプロイの二大国の主導権の争が次第に強まり、この二国がドイツ統一の鍵を握る候補者であることを浮彫りにさせるだけであった。
即ちウィーン会議では、オーストリア、プロイセンの二大王国の他37の中小領邦でドイツ連邦が結成されたが、連邦自身政府を持つわけでなく単なる協議体にすぎなかった。そしてその中で二大勢力が争うことになったのである。
だが一方では、ロシア、フランスに囲まれた中央ヨーロッパで、同一言語を使用するドイツ民族が何等かの団結を求める声はひとびとの中で次第に高まっていたし、他方小国分立が、産業、経済の発展の障害として目立ち始めて来た。これらのことが、単に君主の覇権争奪戦以外の統一への原動力となったことは見逃せない事実である。
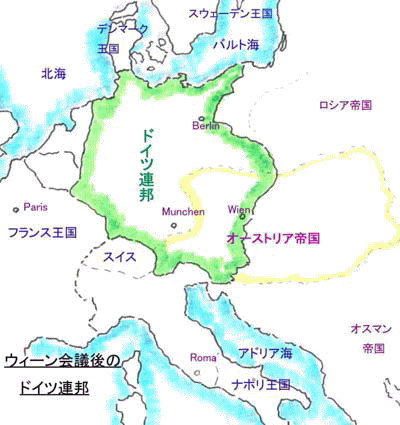
ところで、ウィーン会議で取りきめられたドイツ連邦の構成部分には、後のドイツ帝国に統一された諸領邦の他に、ルクセンブルク、リヒテンシュタインも含まれていた。そしてオーストリアは後にはドイツ帝国の中核となったブロイセンよりも広い領土を保有していたのである。
1863年からのデンマーク戦争の後、オーストリアはデンマークと同君連合(同一君主を首長とする独立国家をいう)のホルシュタインを併合、プロイセンはシュレスヴィヒを獲得した。
1866年にはリヒテンシュタインが、1867年にはルクセンブルクがそれぞれドイツ連邦から離脱した。
1866年のプロイセン、オーストリア戦争で敗れたオーストリアがドイッ連邦から追放されて、ドイツ連邦の範囲はほぼ後のドイツ帝国のそれと等しいものとなったのである。
(この戦争の結果ドイツ連邦は解体され、北ドイツ連邦が結成されたが、このことは後に述べる)。
話を少し前にもどし、1850年前後から切手を発行し始めたドイツ連邦内の諸領邦を以下に掲げる。カタログを見れば判ることであるが、以後につづく説明の便宜上採録する。(ミッヘルカタログ所載の地名のうちベルゲドルフとヘルゴラントは連邦構成領邦ではないので除外)
| 1849年 | 11月1日 | バイエルン王国 | ●切手の表示 |
| 1850年 | 6月1日 | オーストリア帝国 | ●切手の表示 |
| 7月1日 | ザクセン王国 |
●切手の表示 | |
| 11月15日 | プロイセン王国 |
●切手の表示 | |
| 11月15日 | シュレスヴィヒ王国 |
●切手の表示 | |
| 12月1日 | ハノーヴァー王国 |
●切手の表示 | |
| 1851年 | 5月1日 | バーデン大公国 | ●切手の表示 |
| 10月15日 | ヴェルテンベルク王国 | ●切手の表示 | |
| 1852年 | 1月1日 | ブラウンシュヴァイヒ王国 | ●切手の表示 |
| 1月1日 | トウルン・ウント・タキシス | ●切手の表示 | |
| 1月5日 | オルデンブルク大公国 | ●切手の表示 | |
| 9月5日 | ルクセンブルク大公国 | 切手の表示 | |
| 1855年 | 4月10日 | ブレーメン市 | ●切手の表示 |
| 1856年 | 7月1日 | メクレンブルク・シュヴェリン大公国 | ●切手の表示 |
| 1859年 | 1月1日 | ハンブルク市 | ●切手の表示 |
| 1月1日 | リューベック市 | ●切手の表示 | |
| 1864年 | 10月1日 | メクレンブルク・シュトレリッツ大公国 | ●切手の表示 |
39領邦の内切手を発行したのは半数以下の16である。ということは諸領邦の中には、郵便業務を他の領邦に委託したものが可成りあったからである。特にトウルン・ウント・タキシス家は、神聖ローマ帝国以来中央ヨーロッパに広大な郵便綱を保持しており、この当時、縮少したとはいうもののまだ数多くの領邦の郵便業務を掌握ていた。以下その関係を示す。
| 運営主体 | 委託領邦 | |
| オーストリア | リヒテンシュタイン | |
| プロイセン | アンハルト公国 | |
| ワルデック候国 | ||
| ザクセン | ザクセン・アルテンブルク公国 | |
| トゥルン・ウント・タキシス | ヘッセン選定候国 | |
| ヘッセン大公国 | ||
| ナッソウ公国 | ||
| ザクセン・ヴァイマール大公国(註1) | ||
| ザクセン・ユーブルク・コーダ公国 | ||
| ザクセン・マイニンゲン公国 | ||
| シュヴァルツブルク・ゾンデルスハウゼン候国 | ||
| シュヴァルツブルク・ルードルシュタット候国 | ||
| ホーエンツォレルン・ヘッヒンゲン候国 | ||
| ホーエンツォレルン・ジグマリンゲン候国 | ||
| ロイス兄系候国 | ||
| ロイス弟系候国 | ||
| リッペ・シュムブルク候国 | ||
| リッペ・デトモルト候国 | ||
| ヘッセン・ホンブルク伯領 | ||
| フランクフルト・アム・マイン市 |
この他ハンブルク・ブレーメン・リューベックの3都市でも郵便業務を取り扱っていた。これらの諸領邦の大部分は小国で、小さいものは人口5万ないし10万程度の小邦であるが、中にはヘッセン大公国のように八口100万をこえる国で、郵便権を持たないところもあった。いずれにしても19世紀半ばで、このような小邦が存在し、しかも領地がモザイク模様のように分散していたということは極めて特徴的なことであり、それがまたドイッ統一を遅らせたことともなったのである。
1866年のプロイセン・オーストリア戦争に勝ったプロイセンは、オーストリアの勢力下にあったホルシュタインの他、オーストリアに加担した、ハノーヴァー、ヘッセン選帝侯、ナツソウ、フランクフルトを吸収した。そしてオーストリアをドイツ連邦から追放し、北部ドイツの22の領邦、都市により北ドイツ連邦を結成し自らその盟主としてドイツ統一に大きな前進を果したのである。
北ドイツ連邦の結成は同時に北ドイツ郵便連合の成立となったのだが、それに先立ちプロイセンはトゥルン・ウント・タキシス家の3郵便権を買収した。その交渉は困難を極めたというが、プロイセンの郵便長官ステファンの努力により、1867年1月28日協議成立、同年6月30日350年の歴史を持つトゥルン・ウント・タキシス家は郵便業務から手を引き、その権利はプロイセンに移った。
1868年1月1日から北ドイツ郵便連合が発足し、それまで発行されていた各領邦、都市の切手は一部例外を除き廃止された。カタログでNorddeutscher Postbezirk(北ドイツ郵便地区)として記載されている切手が発行されたわけである。これによって自邦の切手の発行が停止されたのは次の諸領邦と都市である。
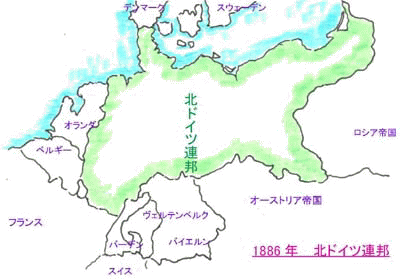
プロイセン
ザクセン
メクレンブルク・シュ.トレリッツ
メクレンブルク・シュヴェリン
オルデンブルク
ブラウンシュヴアイヒ
ブレーメン
リューベック
ハンブルク
 |
 |
 |
 |
| ターラー・グロッシェン | グルデン・クロイツァー | ||
北ドイツ連邦の結成はドイツ統一一への大きな足がかりとなったが、まだ重要な問題を残していた。
貨弊制度の統一である。ドイツの貨弊制度については部会報42号に小生が紹介しているが、大まかに云えば、北部地区はターラー・グロッシェンという制度があり、南部地区はグルデン・クロイツァーという制度で共に銀本位であった。北ドイツ郵便地区の切手が、グロッシェン、クロイツァ、ハンブルクシリングの3本立で発行されたのはそのためであり、通貨の統一は1875年金本位制採用によって漸く完成したのである。なお北ドイッの名が示すように、南のバイエルン、ヴュルテンベルク、バーデンは北ドイツ連邦にも、従ってまた北ドイツ郵便連合にも参加しなかった。これらの領邦が統一ドイツの傘下に入るのは普仏戦争で勝ったブロイセンがドイツ帝国を宣言したときである。
註 下から牧世話人のドイツの貨幣制度の紹介記事「グロッシェンとクロイツァー」にリンクします。
普仏戦争でプロイセンは圧勝し、1871年ドイツ帝国は成立した。ドイツ帝国は4王国、6大公国、5公国、7侯国、3自由市で形成されることとなった。そしてこの体制は第一次大戦でドイツが共和制になるまで続く。但し、統一されたといっても、それを構成する諸領邦は独立した君主、政府、議会を持って、直接地方の政治に当っていた。勿論ドイツ帝国はプロイセン王が世襲する皇帝を戴き、帝国政府と帝国議会を持ち、軍事・外交の権力を掌握した。従来の連邦制度よりは遥かに権力の集中は行われたのである
郵便関係についていえば、バーテンが吸収されて帝国郵便が成立したわけである,然しながら南部での、というよりフロイセンに次ぐ最大の領邦バイエルン王国は郵便権を手離さなかった。
プロイセンの宰相ビスマルクは郵便・電信の留保権と引きかえに帝国への参加を求めたのである。バイエルンのこの特権はワイマール共和国成立後の1920年6月までつづく。またヴュルテンベルクでは帝国郵便が導入されたのは1902年であり、官用郵便については1920年3月まで権利を保有しつづけ
たのである。
別表は目本で明治42年(1909年)に発行された世界地理概要という本に記戴された当時のドイツ帝国の構成諸邦の一覧表てある。大小とりまぜて一つの帝国を構成する状況が判然として興味深い
統一された帝国郵便の切手は1872年6月1日に発行され、北ドイツ郵便地区の切手は同年一杯で流通は停止された。注意しなければならないのは、前に述べたように貨弊制度の統一か1875年であったため、始めて発行された切手は、グロッシェン建とクロイツァー建の二系統のものがそれぞれの地区で使われたこと、及びハンブルク・シリング建の北ドイツ郵便地区の切手は1874年12月31日まで使用されたことである
 |
 |
 |
 |
| ターラー・グロッシェン | グルデン・クロイツァー | ||
1918年11月のドイツの敗戦はドイツ帝国のみならず、それまで君主制をとって来た諸領邦すべてが共和制に移行することになった。Volksstaat Bayern、Freistaat Bayern、及びVolksstaat Württembergと加刷された切手が発行されたのはそのためである。両国とも加刷でない正刷切手も発行されたが1920年4月1日以後はドイッ郵政に吸収され、極く一部のヴュルテンベルクの官用切手を除き、20年6月30日で使用は停止されドイツの切手の上での統一は終了したことになった。
1925年から29年にかけて当時の州の紋章を図案とした切手が発行された。これによると帝国成立時の領邦は殆んどそのまま残り、特に小領邦が多かったチューリンゲン地方のみグ順に並べると、どうやら当時の州の勢力の序列によったものと思われる節がある。
| 1925年発行 | ||||
 |
 |
 |
||
| プロイセン | バイエルン | ザクセン | ||
| 1926年発行 | ||||
 |
 |
 |
 | |
| ヴェルテン ベルク | バーデン | チューリンゲン | ヘッセン | |
| 1928年発行 | ||||
 |
 |
 |
 |
 |
| ハンブルク | メクレンブルク シュヴェリン | オルデンブルク | ブラウン シュヴァイヒ | アンハルト |
| 1929年発行 | ||||
 |
 |
 |
 |
 |
| ブレーメン | リッペ・ デトモルト | リューベック | メクレンブルク シュトレリッツ | シャウムブルク リッペ |
最後に蛇足と付け加えるならば、これら各州から自治権を取り上げ中央集権国家にしたのはヒトラーであった(1933年)。
そして戦後現在の西ドイツは再び連邦共和国となっているのである。
(完)
編集あとがき
ここに表示した切手画像は主にドイツ切手部会所蔵のものからスキャンして載せてあります。ザクセンの一番切手「赤の3」は部会員の方の画像借用です。
ザクセンの「赤の3」については、この高価な切手は流石の牧さんも未入手で、生前入院先のベットの上で熱っぽく語っていたことが思い出されます。
「切手でたどるドイツ統一への歩み」は切手画像の入れ替え、注釈の挿入などの編集を逐次加えていきます。