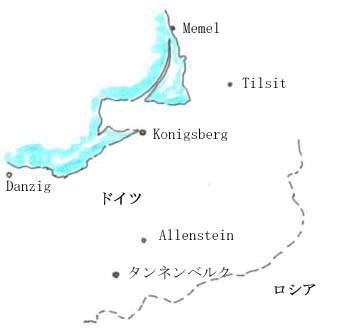
1410年東プロイセンでドイツ騎士団がポーランド・リトアニア連合軍に破れたこの地でスラブ民族に対するゲルマン民族の復讐戦を果たしたことになる。
11世紀以降のドイツ人の東方植民とはとは別にキリスト教の布教を題目にする「ドイツ騎士団」の軍事植民が進んでいた。先住民を征服していく過程でスラブ民族と戦闘があり、1242年にもロシアに大敗している。それだけにドイツ人にとってタンネンブルクでロシア軍を破ったことは快挙であった。
| 第1回 | ヒンデンブルク切手とは |
| 第2回 | ヒンデンブルク切手の年表 |
| 第3回 | ヒンデンブルクとはどういう男 |
| 第4回 | ヒンデンブルク切手登場 |
| 第5回 | メダル型シリーズ (1) |
| 第6回 | メダル型シリーズ(2) |
| 第7回 | メダル型シリーズ 鉤十字透 |
| 第8回 | メダル型シリーズ 鉤十字透 続き |
| 第9回 | メダル型シリーズ 鉤十字透 続きの続き |
| 第10回 | 占領地消印について |
| 第11回 | オステン加刷 |
| 第12回 | エルザス・ロートリンゲン加刷 |
| 第13回 | ルクセンブルク加刷・他 |
| ところでヒンデンブルクとはどういう男であったか。 彼は1847年プロイセンのユンカーの家に生れた。ユンカーというのは土地貴族である。ドイツ東部は昔はスラブ民族が住んでいた土地だが、ドイツは東方へ進出し、ドイツ騎士団の武士に土地所有と農奴所有の特権を与えて領土を拡張した。プロイセンではユンカー出身の官吏、軍人が多く輩出し、ユンカーこそプロイセンの、従って後のドイツ帝国の骨幹をなす階級となったのである。ヒンデンブルクは軍人となったがあまり出世せず退役となった。ところが第一次大戦が始まると現役に復帰、第8軍司令官となったのが幸運の始まりであった。第8軍は東部でロシア軍と戦ったがタンネンベルクの会戦で大勝利をおさめたが彼は一躍英雄に祭り上げられた。その後彼は参謀長となり位人身を極めたことになる。 1918年秋、国内に革命が起こり敗戦は不可避となった時、彼は参謀次長ルーデンドルフと謀ってカイゼルの退位を迫った。カイゼルの退位が停戦の絶対条件とみたからである。戦争は終わったが国内の混乱はつづいた。ワイマール憲法は民主主義を保障したが、与えられたものは自由でなく無秩序と混乱だけであった。共和国初代大統領エーベルトの属する社会民主党は左右のはさみ討ちにあい、ドイツ再建の任を果たせぬままに1925年エーベルトは病死した。 ヒンデンブルクは民主主義の信奉者ではなかった。むしろ心情的には帝政論者であった。そしてそもそもが政治家ではなかった。彼の考え方は「ドイツは戦に負けたのではない、国内の社会主義者共のために負けたのだ」ということばに要約される。正に典型的なプロイセン軍人であった。唯彼には他の誰もが持っていないもの「タンネンベルクの英雄」というレッテルがあった。そして国民投票という大統領選挙にはこのレッテルがものをいう。彼は1925年と32年の選挙にそれぞれ勝ち1934年の死ぬ日まで大統領の椅子に座ることになる。 前号の年表を思い出していただきたい。彼の在任期間中、ドイツは着々と外交勝利をおさめ、大戦で失われた地位を取り戻した。然しこれは実に彼の手腕ではなく、唯唯ソビェトの勢力伸張をおそれた欧州各国が反共の砦としてドイツの復興を認めざるを得なかっただけでのことである。その意味でも彼はツイていたということであろうか。 然し彼が再選された時既に85才であった。結局彼自身が「ボヘミアの伍長」と軽蔑していたヒトラーを首相にせざるを得なくなりナチス政権への橋渡しをすることになってしまった。退け際を誤った人物の典型的な見本である。 註)タンネンベルクの戦い |
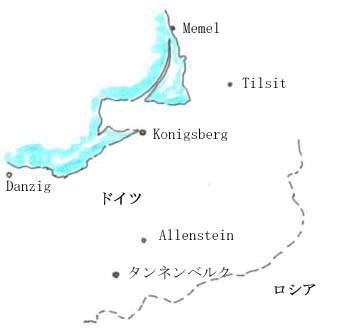 | 第一次大戦の緒戦の東部戦線で侵入したロシアの第一軍団、第二軍団を各個撃破で破った。 1410年東プロイセンでドイツ騎士団がポーランド・リトアニア連合軍に破れたこの地でスラブ民族に対するゲルマン民族の復讐戦を果たしたことになる。 11世紀以降のドイツ人の東方植民とはとは別にキリスト教の布教を題目にする「ドイツ騎士団」の軍事植民が進んでいた。先住民を征服していく過程でスラブ民族と戦闘があり、1242年にもロシアに大敗している。それだけにドイツ人にとってタンネンブルクでロシア軍を破ったことは快挙であった。 |